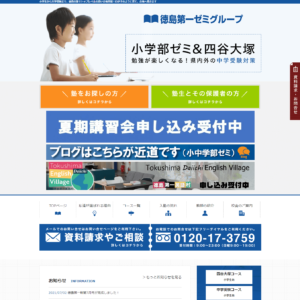【中学生向け】理科科目の苦手を克服する方法を紹介

中学校に進学すると「急に勉強が難しくなった」と感じる生徒も少なくありません。中には、理科科目に苦手意識を持ってしまう人もいることでしょう。そこで今回は、理科科目の苦手を克服するための勉強方法を、3つピックアップして紹介します。本記事を参考に、ぜひ理科科目への苦手意識を払拭してください。
「わかった気」をなくす
理科の学習において多くの中学生が陥りがちな問題として「わかった気になる」ことが挙げられます。とくに理科に対して「暗記教科」という先入観を持っている生徒は、重要語句や用語さえ覚えていれば得点できると考えがちです。
しかし実際には、そうした表面的な暗記に頼る学習法では、真の理解に至らず、テストで応用力を求められた際に対応できないという問題が生じています。こうした傾向の背景には、理科用語が比較的直感的で分かりやすい言葉で構成されているという特徴があります。
たとえば「等速直線運動」という用語を見れば、多くの生徒は「等しい速さでまっすぐ進む運動」と文字通りの意味を受け取ることができます。このように語句の意味がそのまま現象を表しているため、用語の意味がわかれば内容も理解できたような錯覚に陥りやすいのです。
この「わかった気」は、実際には演習不足につながります。語句の意味を理解しただけで満足し、問題演習をほとんど行わないままテストに臨んでしまう生徒が少なくありません。
その結果、テスト本番では知識をうまく使いこなせず「どこかで見たことはあるけれど、正確に思い出せない」といった状態になり、思うように点が取れないという事態に陥ってしまうのです。
理科において大切なのは、語句の意味を知ることだけでなく、それがどのような場面で、どのように使われるのかを理解し、実際の問題に適用する力を養うことです。
つまり、演習を通じて知識を定着させ、運用できるようにする学習が必要不可欠であるということです。このような観点からも「わかった気」を排し、実際に問題を解くという経験を積むことが、理科の理解と成績向上には不可欠だといえるでしょう。
問題演習を徹底する
高校受験における理科の攻略法として、最も効果的なのは「知識の定着」と「演習による慣れ」の徹底です。理科は暗記だけで乗り切れる科目ではなく、まずは基礎知識を固めたうえで、それを実際に使いこなす力を養うことが求められます。
学習の第一段階では、重要語句とその仕組み、関連性を理解することが不可欠です。そのためには、まとめノートを作成したり、重要語句が整理された問題集を活用すると効果的です。
とくにまとめノートは、作成の過程で知識を頭の中で整理でき、完成したノートを見返すことで記憶の定着にも役立ちます。図や表を使いながら、例えば消化器官と血液循環のように関連する内容を並べて描くことで、理解をより深めることができます。
ただし、入試直前の限られた時間では、まとめノート作成に多くの時間を割くのは非効率です。そのような場合は、すでに重要事項が整理されている問題集などを使って、効率よく知識を確認・暗記する方法が推奨されます。
知識のインプットがある程度済んだら、次は演習に移りましょう。問題を繰り返し解くことで、「わかったつもり」だった部分を洗い出すことができ、理解の曖昧さを明確にできます。また、出題形式に慣れることにもつながるため、実戦力の向上にも効果があります。
問題集を選ぶ際は、目的に応じたものを選ぶことが大切です。定期テスト対策には基礎が中心の簡単な問題集、公立高校の入試対策には全国の公立入試問題を収録したもの、そして難関校を目指す場合は難問に特化した問題集が適しています。
また、参考書と問題集がセットになったものは、基礎から復習したい場合に特に有効です。このように、理科の学習では単なる暗記にとどまらず「知識の定着→問題演習→出題形式への慣れ」というステップを意識することが、得点力アップのカギとなります。
苦手な単元を正しく把握する
理科の学習を進めるうえで、重要なのは自分の苦手な単元を明確に把握し、それに対して適切な対策をとることです。とくに問題演習を繰り返す中で「解けない」「理解できない」と感じる単元が出てきた場合、それをそのままにせず、立ち止まって原因を確認する姿勢が求められます。
理科には物理・化学・生物・地学という4つの分野があり、それぞれ内容やアプローチの仕方が異なります。数学のように前の単元の理解がそのまま次に直結する「積み上げ型」ではないため、得意な単元と苦手な単元がはっきり分かれやすいという特徴があります。
たとえば、生物の内容はスムーズに理解できても、物理の計算問題に苦手意識を持つといったことは珍しくありません。そのため、苦手な単元に気づいた時は「どの分野に属するのか」をまず整理することが第一歩です。そして、その分野ごとに必要な知識や考え方を再確認し、重点的に復習していくことが効果的です。
例えば、物理であれば公式の意味と使い方を理解する、化学であれば反応式や計算に慣れる、生物なら図解や仕組みをビジュアルで理解する、地学であれば地形や天体の動きを整理するなど、それぞれに合った学習方法をとることが重要となります。
また、苦手単元を一気に克服しようとするのではなく、1つずつていねいに潰していくことが成功のカギです。短期間で成果が出るとは限りませんが、地道に継続していけば、やがて模試や本番の試験で結果として表れてくるはずです。焦らず、諦めず、少しずつ前進する姿勢が、理科の実力を確実に高めていくうえで最も大切だと言えるでしょう。
まとめ
理科に苦手意識を持つ中学生にとって、ただ暗記するだけではなく、理解を深めて実践に活かす学習が不可欠です。本記事では「わかった気」をなくすこと、問題演習を繰り返して出題形式に慣れること、自分の苦手単元を正しく把握して対策することの3点を紹介しています。理科は積み上げ型ではない分、分野ごとの学習の工夫が必要ですが、ていねいに取り組めば必ず力がついてきます。地道な努力が点数アップに直結するので、焦らず自分のペースで苦手克服を目指しましょう。
-
 引用元:https://tokushima-gakushujuku.info/
「四国進学会G」は、小~高を対象にした難関校の受験対策に強い学習塾です。
引用元:https://tokushima-gakushujuku.info/
「四国進学会G」は、小~高を対象にした難関校の受験対策に強い学習塾です。-
Point
進学校の受験に特化! 国立大合格もバッチリ!
-
Point
少人数クラスで一人ひとりを徹底サポート
-
Point
保護者からの信頼が厚い
-
Point